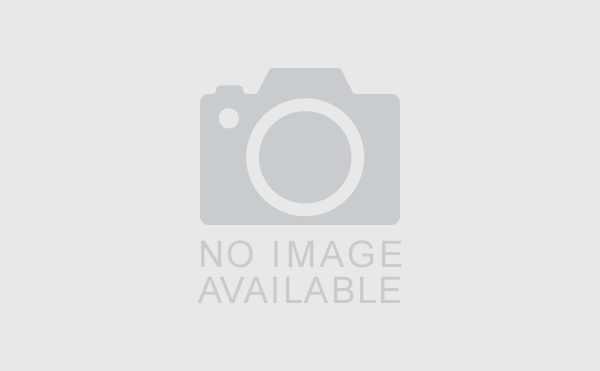県央管内の主な火災原因(令和6年)
県央管内における令和6年中の総出火件数は73件で、前年より7件増加しました。
これは、およそ5日あたり1件の火災が発生したことになります。
令和6年中の住宅火災被害状況
73件の火災のうち「建物火災」が41件、「その他の火災」が25件、「車両火災」が6件、「船舶火災」が1件でした。
建物火災の中でも住宅火災が17件発生しており、その約半数が全焼火災となっています。火災を身近なことと捉え、火災原因の傾向から火災予防を徹底しましょう。
令和6年中の主な火災原因
令和6年中の主な出火原因は、たき火、たばこ、こんろ、ストーブや電気機器などで、人のちょっとした油断や不注意が起因となって火災に至る事例がみられ、大きな被害を及ぼしている事例もあります。
ストーブを原因とした火災
令和6年中のストーブが原因の火災件数 3件
ストーブが原因の火災による被害 全焼2棟、半焼2棟、部分焼5棟、ぼや2棟
死者1名、負傷者3名
ストーブ火災事例
- ストーブの近くに洗濯物や雑誌などの燃えやすいものを置いている。
- ストーブの給油時にキャップの緩みなどで燃料が漏れ、着火する。
- ストーブに誤ってガソリンや軽油を給油する。

火災予防ポイント
- ストーブの近くに、燃えやすいものを置かない。ストーブの上で洗濯物を乾かさない。
- ストーブ給油時にキャップがしっかり閉まっていることを確認する。
- 寝るときやその場を離れるときは、ストーブの火を消す。
- ストーブの燃料タンクを明確にしておく。

たき火を原因とした火災
令和6年中のたき火が原因の火災件数 16件
たき火を原因とした火災による建物被害 全焼2棟、部分焼4棟、ぼや1棟
負傷者1名
たき火から建物や山林に延焼し、被害が拡大することがあります。特に、強風時の被害は甚大なものになる可能性があります。
たき火の火災事例
- 刈り取った枯草等を焼却していて、風に煽られ、小屋に燃え移った。
- 雑草等を畑で焼却中、その場を少し離れたところ、燃え広がって車両に延焼した。
- ドラム缶で焼却していた廃材等の火の粉が建物に着火した。

火災予防ポイント
- たき火は原則禁止!例外的に焼却できる場合であっても、みだりに焼却しない!
- 水バケツ、消火器などを準備する。
- 気象状況を確認し、風の強い日や乾燥している日は行わない。
- 「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を事前に消防署へ提出又は連絡する。(実施状況を把握するものであり、届け出したことで焼却行為を許可するものではありません。)

電気機器等を原因とした火災
令和6年中の電気機器が原因の火災件数 7件
電気機器が原因の火災による建物被害 全焼8棟、部分焼5棟、ぼや2棟
負傷者1名
電気機器火災事例
- 夏場の車内など高温環境下にモバイルバッテリーを放置する。
- 非純正品の粗悪なリチウムイオンバッテリーを電気機器の電源として使用する。
- 膨張して劣化したリチウムイオンバッテリーを電気機器の電源として使用する。

火災予防ポイント
- プラグは定期的に乾いた布などで清掃する。
- 使用しない電気機器の電源プラグは抜く。
- モバイルバッテリーを使用する電気機器を、夏場の車内などの高温環境下に放置しない。
- バッテリーはできるかぎり純正品を使用する。
- 膨張などの変形のある又は異常に高温となるバッテリーは使用しない。

※ 住宅電気火災に関連するリンクはこちらから
※ 電池・バッテリー「ごみ処理施設での発火」(nite映像資料)
※ モバイルバッテリー「リコール製品のモバイルバッテリーから発火」(nite映像資料)
たばこを原因とした火災
令和6年中のたばこが原因の火災件数 4件
たばこが原因の火災による被害 全焼1棟、半焼1棟、ぼや1棟
たばこ火災事例
- 消火不十分な吸殻をごみ箱などに捨てる。
- 消火不十分なたばこの火が、灰皿に溜まった大量の吸殻に燃え移る。
- たばこの火種が布団、座布団等に落下。

火災予防ポイント
- 灰皿には、水を入れておく。
- 灰皿はこまめに清掃し、吸殻を溜めない。
- 寝たばこは絶対にしない、させない。
- たばこのポイ捨てはしない。
こんろを原因とした火災
令和6年中のこんろが原因の火災件数 7件
こんろが原因の火災による被害 全焼2棟、部分焼1棟、ぼや3棟
負傷者1名
こんろ火災事例
- 魚グリル等の清掃が不十分で付着した油脂に着火。
- こんろを消し忘れたことにより、空焚き状態となり、過熱され出火。
- 揚げ物調理中にその場を離れてしまったことにより、天ぷら油が過熱され出火。

火災予防ポイント
- 調理中は、絶対にそばを離れない。
- こんろの周りに燃えやすい物を置かない。
- 換気扇や壁、魚グリル等などは、こまめに清掃する。
- 過熱防止装置付きのこんろを使用する。